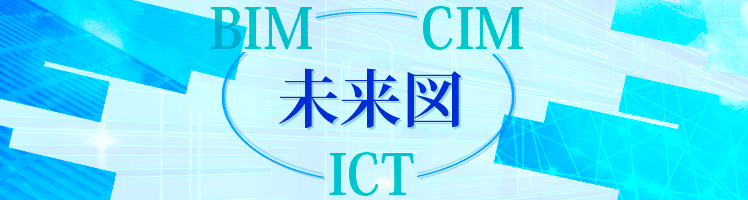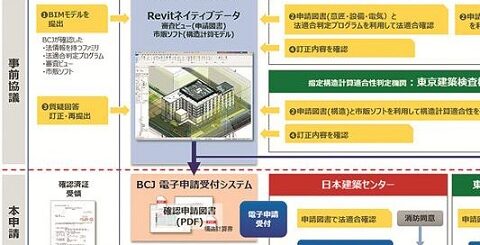【BIM/CIM未来図】ウエスコ㊥ 計測と設計の密接な連携強化/業務多様化にシームレス対応
ウエスコの強みは計測部門と設計部門を持つことだが、これまでは両軸がうまく連動していなかった。社内のBIM/CIMを先導する3次元技術委員会の中心メンバーである冨田修一技術部設計課課長は「BIM/CIMの原則化を機に3次元対応が強く求められる中で、両部門の連携する機会が徐々に増えてきた」と明かす。委員会がその橋渡し役にもなっている。

計測部門は2008年にMMS(モービルマッピングシステム)を導入したのを機に、現在はレーザードローンや地上レーザースキャナ、ナローマルチビーム無人ボードなど多種多様な計測機器を保有し、陸空それぞれの広範囲な3次元計測を得意としている。岡山測量課で3次元計測グループに所属する草加大輝主任は「正直これまでは計測した地形図データを設計部門がどう活用しているか知らずに業務を進めていた。現在の3次元データ活用では設計担当と顔を突き合わせて仕事に参加するようになった」と説明する。荒木組と連携した岡山県内初のICT工事も両部門の連携効果が発揮された。
冨田氏は「当社が保有する技術を生かすには両部門が密接に連携し、シームレスに業務を進めていくことが欠かせない」と考えている。近年のBIM/CIM関連業務では発注者側に具体的な活用方法を提示し、BIM/CIMの導入目的を明確に示す必要性を求められており、それを実現するために両部門が連携意識を強めるようになった。これからは最適な地形計測方法や3次元モデル詳細度、さらには閲覧に有効なソフトウェアを瞬時に提案することで「多様なBIM/CIM要求にも対応していきたい」と力を込める。
設計部門では同業他社がBIM/CIMの推進組織を置く傾向が強い中で、あえて同社は案件ごとに担当者が3次元対応を進めていく流れを重要視している。3次元技術委員会には各部門から技術者が兼務で参加しており、各メンバーがそれぞれの部署の推進役を務める役割も担っている。寄せられた情報はメンバーを通じて委員会で一本化し、委員会がBIM/CIM推進組織として機能している格好だが、岩元浩二執行役員技術推進本部長は「一部の人にナレッジがとどまるのではなく、組織として技術者を育てていきたい」と、あくまでBIM/CIMの業務を進めるのは設計担当者であるというスタンスを崩さない。
これまでに20件を超える業務でBIM/CIM活用をしてきた冨田氏には社内から業務上の相談が絶えない。「国交省が原則化を打ち出したことを機に、設計部門の意識は大きく変わり、BIM/CIMに真正面から向き合う設計者が増えてきた」と実感している。計測部門も3次元対応の業務が拡大するにつれ、草加氏は「先導役が着実に育っている」と説明する。21年8月には3次元関連の業務窓口を担う空間情報事業部を新設し、組織の枠組みも進化しつつある。同社はBIM/CIMの進展を足掛かりに、3次元を活用したサービス提供のための新たな業務の枠組みも検討し始めた。

ほかの記事はこちらから
【B・C・I 未来図】2021年以前の記事はこちらから
建設通信新聞電子版購読をご希望の方はこちら