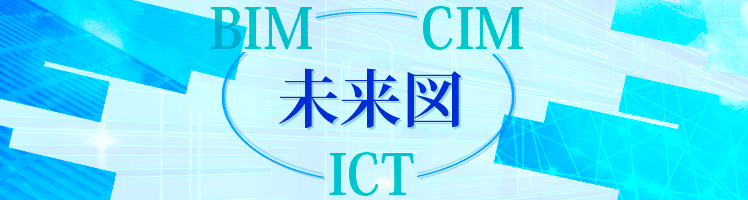【BIM/CIM未来図-建設技術研究所②】簡易なモデル使い時短効果/外注せず3次元に取り組む
建設技術研究所の中部支社が、国土交通省中部地方整備局設楽ダム工事事務所から受託した設楽ダム関連施設詳細設計業務を完了させたのは1年前のことだ。契約期間は約11カ月。業務を担当した河川部水工室の新谷裕美氏は「わたし自身初のBIM/CIM挑戦だったが、業務スタート時から3次元で設計を進めながら、BIM/CIM活用の効果を得ていきたい」と考えていた。しかも協力会社などへの外注はせず「電子納品も含め、そのすべてを内製で取り組みたい」との決意もあった。
社を挙げてBIM/CIM活用にかじを切る中で、中部支社内の活用実績は当時まだ1件しかなかった。国交省がBIM/CIM原則適用時期を当初の2025年度から23年度に前倒ししたのは20年度に入ってからだ。岡嶋義行水工室室長は「原則化を見据え、少しでも対応数を増やしていきたい」との思いを持っていたタイミングで、新谷氏から相談があり「前向きな姿勢を尊重したい」と背中を押した。
新谷氏は、取水堰場所の洗い出しなど計画の課題点を抽出する際の検討に3次元が有効と考えていた。受注者希望型業務であったため、BIM/CIM活用の計画書をまとめ、発注者から了解を得たのは受注から3カ月が過ぎた頃だった。既に基本設計で全体の概略は決まっていたが、より最適な配置を導き出したいと、あえて現地の3次元測量を実施し、その成果を待っている間に管理用道路などのモデルを作成した。「細かなディテールにこだわらず、LOD(詳細度)100の簡易なモデルで進めたことで1.5カ月の短期間でモデルの検証を完了することができた」と振り返る。
取水堰の比較検討では発注者に3案を提示した。モデルの視覚的効果によって構造物の距離感がイメージしやすく、協議もスムーズに進んだ。東京本社技術統括部BIM/CIM推進センターの藤田玲センター長は「業務上の比較検証や合意形成の部分がBIM/CIM活用の大きなメリットの一つだけに、業務当初から3次元設計を進めてきた効果は大きい」と説明する。

取水堰の最終位置を合意した段階で、管理用道路法線の見直しやバイパス線形の精査も進めてきた。新谷氏は「その間の約3カ月間を使い、オペレーターにオートデスクのBIMソフト『Revit』の操作スキルを学んでもらった」と明かす。BIM/CIMソフト『Civil3D』については社内講習会を実施し、テキストも整えているが、建築分野でよく使われるRevitを橋梁下部工など構造物の設計に採用するケースは限られていた。このため、中部支社初のトライアルとしてRevit活用も踏み込んだ。
現状地形や管理用道路のモデリングにはCivil3D、取水堰や県道付け替え道路などの比較検証用に使った簡易なモデルは3次元モデリングソフトのSketchUp、そして取水堰本体の最終モデリングにはRevitを活用した。新谷氏は「対象となるモデルの詳細度によってソフトを使い分けることがスムーズに業務を進める要因になった」と力を込める。